朝刊のTV欄によれば「▽手作りすごろくの楽しみ/▽家族の思い出をゲームに」という内容だということで、NHK総合の関東地方ローカル番組「こんにちは いっと6けん」を見てみました(午前11:05〜)。
ボードゲームに詳しい郷内邦義さんが800を超えるボードゲーム・コレクションの中から十数のもの(スコットランド・ヤードなど)を持って登場です。ドイツ産のボードゲームがやっぱり出来がよくて木製でいい感じ、とのことです。
とはいえ、天下のNHK。具体的に「このゲームがお勧め!」なんて商品紹介をするわけではありません。商品名を出さずに3つくらいボードゲーム紹介をしていましたが。
オリジナルのボードゲーム作成について番組は進みます。
とある一家のもとを訪れ、その家族の1年の思い出をもとに双六作成をするという内容です。
1)イベント(写真・思い出事例)を選ぶ。
2)各イベントをマスとして整理。(双六のマスにするためのフォーマットシートが登場です)
3)各イベントを時計回りに並べる。
4)各イベントにゲーム内効果(nマス進む/nマス戻る/振り出しへ/もう1回サイコロを振るなど)を配置
5)完成
「進む」は「戻る」の2倍くらいあった方が、ゲームが進みやすくて盛り上がるだろうとのコメントもあったような気がします。
こういったシンプルな双六で盛り上がる様子を見ると、戦前の新聞に付いていた付録のボードゲームと同じく、ゲームはルールや構成物の立派さだけではないと感じさせられます。
その場にいる面々に、適当な話題を提供することができればそれだけで十分なのでしょう。サイコロの出目が「1だ」「2だね」と騒ぐだけで十分楽しめるものなのです。
場の支配権をサイコロに委ねることで、その場にいる面々のあいだに優劣はなくなり、等位置の立場に立つことができるからなのでしょうか。
(関連ページ)郷内邦義さんのHP
http://www.gohnai.com/ ゴーナイドットコム
■最近の読書

「あたりまえだけど、とても大切なこと 子どものためのルールブック」著:ロン・クラーク/訳:亀井よし子/刊:草思社/満足度:★★★★★(詳細情報/楽天ブックス利用)
○どんな本?
米国ディズニー社主催の全米の優秀教師選定イベントで賞された小学校教師による「子どものためのルールブック」です。
ルール単独を眺めただけでは一瞬驚くようなルールも混ざっていますが、クラーク氏の経験談が各ルールごとに紹介されており、子どもへのしつけ方法を考えるきっかけとなるルールがつまった本です。
言い訳しかできない口下手な大人にとっても、自らの常識・マナーを再考するきっかけとなる良書です。
○ここが素敵
「ルール10 意外な親切でびっくりさせよう」にある「びっくりプレゼント」についての経験談が一番大きな印象を与えてくれます。
なんといいますか、教育の一環で新聞の広告枠を購入してみる――そんな手法だけでもびっくりです。ですが、この広告枠が引き起こす結果の数々――クリントン氏まで登場する結末はぜひともご一読していただきたく思うばかりです。
○知ったきっかけ
TVのワイドショーなどで米国の俳優が絶賛していたという話から興味を持った……というのではふつうっぽいですね。
本書の副題の「子どものためのルールブック」の「ルールブック」というところに、興味を持ったというのが真相です。ゲームのルールを作成する際に役立つ、ルールを紹介するテクニックを読んでみたかったという理由なのです。
ルール+ルールの存在理由+運用例/経験談の3段構えがわかりやすさの基本かな、そんな結論が本書の読後の印象です。
ボードゲームに詳しい郷内邦義さんが800を超えるボードゲーム・コレクションの中から十数のもの(スコットランド・ヤードなど)を持って登場です。ドイツ産のボードゲームがやっぱり出来がよくて木製でいい感じ、とのことです。
とはいえ、天下のNHK。具体的に「このゲームがお勧め!」なんて商品紹介をするわけではありません。商品名を出さずに3つくらいボードゲーム紹介をしていましたが。
オリジナルのボードゲーム作成について番組は進みます。
とある一家のもとを訪れ、その家族の1年の思い出をもとに双六作成をするという内容です。
1)イベント(写真・思い出事例)を選ぶ。
2)各イベントをマスとして整理。(双六のマスにするためのフォーマットシートが登場です)
3)各イベントを時計回りに並べる。
4)各イベントにゲーム内効果(nマス進む/nマス戻る/振り出しへ/もう1回サイコロを振るなど)を配置
5)完成
「進む」は「戻る」の2倍くらいあった方が、ゲームが進みやすくて盛り上がるだろうとのコメントもあったような気がします。
こういったシンプルな双六で盛り上がる様子を見ると、戦前の新聞に付いていた付録のボードゲームと同じく、ゲームはルールや構成物の立派さだけではないと感じさせられます。
その場にいる面々に、適当な話題を提供することができればそれだけで十分なのでしょう。サイコロの出目が「1だ」「2だね」と騒ぐだけで十分楽しめるものなのです。
場の支配権をサイコロに委ねることで、その場にいる面々のあいだに優劣はなくなり、等位置の立場に立つことができるからなのでしょうか。
(関連ページ)郷内邦義さんのHP
http://www.gohnai.com/ ゴーナイドットコム
■最近の読書

「あたりまえだけど、とても大切なこと 子どものためのルールブック」著:ロン・クラーク/訳:亀井よし子/刊:草思社/満足度:★★★★★(詳細情報/楽天ブックス利用)
○どんな本?
米国ディズニー社主催の全米の優秀教師選定イベントで賞された小学校教師による「子どものためのルールブック」です。
ルール単独を眺めただけでは一瞬驚くようなルールも混ざっていますが、クラーク氏の経験談が各ルールごとに紹介されており、子どもへのしつけ方法を考えるきっかけとなるルールがつまった本です。
言い訳しかできない口下手な大人にとっても、自らの常識・マナーを再考するきっかけとなる良書です。
○ここが素敵
「ルール10 意外な親切でびっくりさせよう」にある「びっくりプレゼント」についての経験談が一番大きな印象を与えてくれます。
なんといいますか、教育の一環で新聞の広告枠を購入してみる――そんな手法だけでもびっくりです。ですが、この広告枠が引き起こす結果の数々――クリントン氏まで登場する結末はぜひともご一読していただきたく思うばかりです。
○知ったきっかけ
TVのワイドショーなどで米国の俳優が絶賛していたという話から興味を持った……というのではふつうっぽいですね。
本書の副題の「子どものためのルールブック」の「ルールブック」というところに、興味を持ったというのが真相です。ゲームのルールを作成する際に役立つ、ルールを紹介するテクニックを読んでみたかったという理由なのです。
ルール+ルールの存在理由+運用例/経験談の3段構えがわかりやすさの基本かな、そんな結論が本書の読後の印象です。
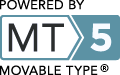
コメントする