■今日の見出し
・三岸節子展
(今日の一言)
投票に行ってきました。
帰宅後、平塚市のページを覗いてみれば、選管による投票率速報、開票速報のページがあるんですなぁ。
平塚市の投票率:56.44%……。6割いきませんでしたか。
(追記22:11)期日前投票などを含めた最終カウントだと、65.19%だそうです。
※ ※
近くのスーパーの日用品売り場で、ボードゲーム「スコットランドヤード」の処分価格を発見。ほぼ半額の¥1500ですか……。さすがに「スコットランドヤード」2つは、いらないからなぁ。予備の備品として買っておく?
 (リンク先は処分価格じゃないですよ)
(リンク先は処分価格じゃないですよ)
半年前には、ボードゲーム「カタン」の処分価格販売もしていましたが、処分価格にしなければならないボードゲームを仕入れてしまうのは、問屋の営業マンが上手いのか、仕入れ担当が無責任なのか……はたして?
 (同じく処分価格じゃないです)
(同じく処分価格じゃないです)
■三岸節子展
平塚市美術館の「生誕100年記念 三岸節子展」最終日を見に行ってきました。
私、浅学でして、三岸節子さんという絵描きさんを知りませんでした。
展示室に踏み入れた私は、その絵から放たれるパワーにただただ見入ることしかできませんでした。
油彩画だけあって、表面はさすがにぼこぼこしています。
塗り固められた油絵の具の層が、平面に対する絵画的技法と組み合わされ、立体感・画面の奥行きを強化しています。
大きな絵は大きいだけでパワーを持ちますが、大きな絵が全体が狂うことなく一枚の絵として存在するためには大きな活力が注ぎ込まれなければならないことを考えると、ただ圧倒されるだけです。
特に印象に残ったのは、「魚とインカの壺」(1951年)、「火の山にて飛ぶ鳥」(1960年)でしょうか。
「魚とインカの壺」は、魚とインカの壺という組合せの妙だけでなく、釘で引っ掻いたような線が作品に緊張感をもたらしているように感じます。
「火の山にて飛ぶ鳥」は、(変なたとえですが)白いムースにチョコパウダーをまぶした感じで、私の食欲に強く訴えかける作品でした。こういうデザインのお菓子というのもいいなぁ。
展示室その2には、絶筆作品「花」がイーゼルに載せられ、絵の具置きなどとともに展示され、作成風景が再現されていました。
額に納められていない「花」は、横から並べることもでき、普段は額のおかげで見ることの難しい、油絵の具の凸凹を把握することができました。
これだけパワーのある展示ならば、閉館40分まではなく、もっと早く見に来るのだったともの惜しく思うのでした。
今日は展示図録を買うつもりはなかったのですが、日記テキストがある程度収録されるということで、ついつい購入してしまいました。展示品につけられた三岸さん自身のテキスト(日記によるものらしい)のパワーが強かったので、日記テキストには非常に心惹かれます。
メモをとってきたテキストを少し紹介しておきます。
「南仏風景(B)」(1969年)そばのテキスト
〈ただ人それぞれの才能、素質、個人差はいかんともなしがたい。おのれの持てる最善をつくすのみである〉
67歳時のテキスト
〈何故絵を描くのか。生活のナリワイなれば。何故絵を描くのか。ただナリワイならば野菜を売ってもよし。小間物屋、菓子屋にてもよし。ただひたすらに絵を描くは、しびれるような満足をえたいがためである〉
公式サイトによれば、続いて、北海道立三岸好太郎美術館、一宮市三岸節子記念美術館でもこの展示は開催されるそうなので、そちらにお住まいの方は一度足を運ばれるのもいいかと思います。
(関連サイト)
・平塚市美術館
(関連書籍)

「炎の画家三岸節子」
著:吉武輝子/刊:文藝春秋/1999年12月(詳細情報 in 楽天ブックス利用)
・三岸節子展
(今日の一言)
投票に行ってきました。
帰宅後、平塚市のページを覗いてみれば、選管による投票率速報、開票速報のページがあるんですなぁ。
平塚市の投票率:56.44%……。6割いきませんでしたか。
(追記22:11)期日前投票などを含めた最終カウントだと、65.19%だそうです。
※ ※
近くのスーパーの日用品売り場で、ボードゲーム「スコットランドヤード」の処分価格を発見。ほぼ半額の¥1500ですか……。さすがに「スコットランドヤード」2つは、いらないからなぁ。予備の備品として買っておく?
 (リンク先は処分価格じゃないですよ)
(リンク先は処分価格じゃないですよ)半年前には、ボードゲーム「カタン」の処分価格販売もしていましたが、処分価格にしなければならないボードゲームを仕入れてしまうのは、問屋の営業マンが上手いのか、仕入れ担当が無責任なのか……はたして?
 (同じく処分価格じゃないです)
(同じく処分価格じゃないです)■三岸節子展
平塚市美術館の「生誕100年記念 三岸節子展」最終日を見に行ってきました。
私、浅学でして、三岸節子さんという絵描きさんを知りませんでした。
展示室に踏み入れた私は、その絵から放たれるパワーにただただ見入ることしかできませんでした。
油彩画だけあって、表面はさすがにぼこぼこしています。
塗り固められた油絵の具の層が、平面に対する絵画的技法と組み合わされ、立体感・画面の奥行きを強化しています。
大きな絵は大きいだけでパワーを持ちますが、大きな絵が全体が狂うことなく一枚の絵として存在するためには大きな活力が注ぎ込まれなければならないことを考えると、ただ圧倒されるだけです。
特に印象に残ったのは、「魚とインカの壺」(1951年)、「火の山にて飛ぶ鳥」(1960年)でしょうか。
「魚とインカの壺」は、魚とインカの壺という組合せの妙だけでなく、釘で引っ掻いたような線が作品に緊張感をもたらしているように感じます。
「火の山にて飛ぶ鳥」は、(変なたとえですが)白いムースにチョコパウダーをまぶした感じで、私の食欲に強く訴えかける作品でした。こういうデザインのお菓子というのもいいなぁ。
展示室その2には、絶筆作品「花」がイーゼルに載せられ、絵の具置きなどとともに展示され、作成風景が再現されていました。
額に納められていない「花」は、横から並べることもでき、普段は額のおかげで見ることの難しい、油絵の具の凸凹を把握することができました。
これだけパワーのある展示ならば、閉館40分まではなく、もっと早く見に来るのだったともの惜しく思うのでした。
今日は展示図録を買うつもりはなかったのですが、日記テキストがある程度収録されるということで、ついつい購入してしまいました。展示品につけられた三岸さん自身のテキスト(日記によるものらしい)のパワーが強かったので、日記テキストには非常に心惹かれます。
メモをとってきたテキストを少し紹介しておきます。
「南仏風景(B)」(1969年)そばのテキスト
〈ただ人それぞれの才能、素質、個人差はいかんともなしがたい。おのれの持てる最善をつくすのみである〉
67歳時のテキスト
〈何故絵を描くのか。生活のナリワイなれば。何故絵を描くのか。ただナリワイならば野菜を売ってもよし。小間物屋、菓子屋にてもよし。ただひたすらに絵を描くは、しびれるような満足をえたいがためである〉
公式サイトによれば、続いて、北海道立三岸好太郎美術館、一宮市三岸節子記念美術館でもこの展示は開催されるそうなので、そちらにお住まいの方は一度足を運ばれるのもいいかと思います。
(関連サイト)
・平塚市美術館
(関連書籍)

「炎の画家三岸節子」
著:吉武輝子/刊:文藝春秋/1999年12月(詳細情報 in 楽天ブックス利用)
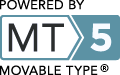
コメントする